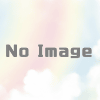政府開発援助(ODA)についての一提言
齋藤 健(技術士、農業部門)
日本のODA金額が1997年をピークにして半減の状態になっているという。最近の2018年の金額は約100億ドルで、米、独、英、仏に次いで世界で5番目であるという。軍事力をバックにできない日本にとってODAは外交の最も大事な手段の一つである。ODAが減少した理由は近年我が国における社会福祉費用が急増したことによると言われる。ODA以外にも軍事費も少なくなってきておりGNPに対しての比率は韓国よりも劣ってきているという。
さてODAには多国間援助と二国間援助とに分かれる。前者は国連とその関連機関例えばWHO,ILO,FAOなどの機関への運営のための拠出金であり、個々の国のGNPなどに比例して金額が決められる。以前も述べたように長い間、日本は米国に次いで第2位の金額を拠出してきた。最近はこの地位を中国に奪われてしまった。二国間援助は開発途上国との間の契約による無償資金援助と技術協力とに分かれる。筆者は長い間 、技術協力のための専門家として働いてきた経験がある。インドネシア、ネパール、ボリビア、フィジーなどの農産加工、流通などについての案件である。これらの経験からODAを効果的にするためのアイデアを提案したい。
それは技術協力に付随して供与された機材の再活用である。筆者はJICAの開発調査案件で90年代後半から2000年代はじめにかけて数回インドネシアの青果物品質や流通改善の調査に従事した。農学部系列では同国で最も歴史と実績があるボゴール農科大学も訪問調査を行った。同大学ではAP-4、(Agricultural Product Processing Pilot Plant)というJICA案件がありジャーフアメンター、遠心分離機、乾燥機からステンレスの豆腐製造装置などが供与されていた。プロジェクトの初めには農水省の研究所から専門家が実験指導に派遣されていたのであるが、筆者が調査した際にはもう期間が終了しておりこれらのプラント機器は埃をかぶって寝ている状態であった。僅かに豆腐製造装置だけが職員によって使われ、出来た豆腐は実費を支払って分けている状態であった。インドネシアには大豆をMucorという毛カビで発酵させたテンペという食品があり微生物を食品として用いる事には抵抗がないはずである。また国内には味の素の発酵工場もある。熱帯土壌から新たに放線菌を選び出して抗生物質を生産するというような試みも大学にあっても良いのではないか、そのためにはこれらAP-4の設備が十分に利用できるのではないかと思った。
もう一つの例はフィリッピンの国立バイオテクノロジー研究所に根粒菌肥料製造パイロットプラントをJICA の無償供与案件として供与したことがある。この研究所では根粒菌の培養培地にココナッツジュースが適していることを発見し、根粒菌肥料製剤の試験生産のためのパイロットプラントの無償供与を求めてきたものである。小型発酵槽、遠心分離機、乾燥機、造粒機などが設置された。根粒菌の研究には北海道の畜産関連の大学が協力していた。根粒菌製剤はピートを担体に使ってサンプル製造には成功したようであり、サンプルも頂いた。その後この機材はどのように活用されているかは全く分からない。根粒菌については他の開発途上国でも関心があり、筆者の調査ではエジプトやネパールの政府研究所や大学でも研究を行っていた。化学肥料の価格が下がったとはいえ、途上国の農民はそれほど簡単に購入することはできないので国立の大学などの研究所が自国で生産可能な肥料を探している。フィリッピンの研究所の根粒菌製造の試みが成功しているのであれば、他の国でも応用が利くのではないかと考える。この様に過去に供与された研究機材の有効活用を目指す事が少なくなったODAを補うことになるのではないか。JICAだけではなくて文部科学省との協力が人材の面から必要とされるであろう。
JICAだけではなく他の国連機関も途上国に無償でバイオ関連機材を供与しているがその中で有効に活用されていない例を多く見かけた。べトナムの小型発酵槽は夏季の水道の温度が高く、殺菌後の冷却や発酵中の温度管理が不可能であった。ブータンの小型発酵槽は殺菌後の冷却時の処置が悪く、ステンレスのジャケットがバキュウムになって変形して使い物にならなくなっていた。機材納入業者も仕様通りに機材を設置して終わりとするのではなく、運転のために必要な教育訓練を特に途上国へ納入するときには心がけて欲しいものである。
出典:Keidanren:ODAを巡る現状と今後の課題;2021年3月11日 No.3491
筆者紹介:発酵工業会社、国連食糧農業機構、ODAコンサルタントとしての経験豊富、日本エッセイストクラブ会員
(食品化学新聞2021.11.04号 掲載)